【西洋の古典からたどる「探究学習」の源流】第3回:思い込みを疑うための道具(フランシス・ベーコン)
- 山中裕太

- 2 時間前
- 読了時間: 12分

「実験する人は蟻のように集めて使うだけ。理屈の人は蜘蛛のように自分から糸を出す。蜂はその間を行く——集めて、そして変える。」(フランシス・ベーコン『ノヴム・オルガヌム』I.95 に基づく意訳)
前回までに、探究の「入口」を整えるためにソクラテスを取り上げ、問いを立て直し、言葉の意味を揃える話をしました。そしてアリストテレスを手がかりに、観察を「説明」に変える骨格(観察・分類・原因)を確認しました。
ただ、入口が整って、観察もして、説明の型も使っているのに、なぜか結論が最初から決まっているように見えることがあります。調べれば調べるほど、ますます自分の考えに都合の良い材料だけが増えていく。この奇妙な偏りを、能力不足や根性論にせず、「人間の頭の癖」として扱うための道具をくれるのが、ベーコンです。
1.ベーコンが気にしたのは「自然」より先にあるもの

ベーコンの代表作の一つが、「ノヴム・オルガヌム(新しい道具/新しい機械)」です。彼は「自然を理解する方法」そのものを作り替えようとしました。ただベーコンがまず問題にしたのは、自然そのものではなく、「自然を見る側のクセ」でした。思い込みを抱えたまま調べると、事実を集めても結論が最初から決まってしまう。ベーコンは、我々が自然を見る前には、見る側(私たち)の頭が勝手に作ってしまう“像”があるとしたのです。
この像を、ベーコンは「イドラ(Idols=偶像)」と呼びます。偶像というと宗教的に聞こえますが、ここではもっと日常的で、もっと厄介です。「思い込み」「決めつけ」「言葉の魔法」「空気」「権威への服従」みたいなものが、調査や議論の途中で静かに入り込み、事実をねじ曲げていく。その“歪み方”を型として示したのが、四つのイドラです。
2.イドラとは何か

ベーコンが「イドラ(idola=偶像)」という言葉で言いたかったのは、単に「人は偏る」という話ではありません。もっと具体的に言うと、私たちの頭は、外の世界をそのまま写す鏡ではなく、知らないうちに像を作り、都合のよい形に整え、見たいものを見せてしまう、ということです。つまり、私たちは事実を見ているつもりでも、実際には“頭が加工した事実”を見てしまう。その加工が積み重なると、観察や議論や学問が、いつまで経っても前に進まない。
ベーコンの出発点には、当時の「学問の停滞」への苛立ちがありました。議論は立派で、言葉は難しく、体系も整っているのに、現実の理解はなかなか増えない。経験を集めても、結局は都合のいい解釈に回収されてしまう。逆に、理屈を積み上げても、現実を動かす力にはなりにくい。彼はここで、「方法が足りない」というより先に、「方法を使う側の頭が、最初から歪むようにできているのではないか」と考えました。
だから彼は、自然を観察する前に、観察者の頭に入り込む“歪み”に注目します。彼の整理は、精神論ではなく、かなり実践的です。歪みは気合で消えない。ならば、歪みがどこから入ってくるかを分類して、名前をつけて、扱えるようにするしかない。こうしてベーコンは、思い込みを四つに分けました。分け方は、「どこから歪みが生まれるか」という発生源の違いです。人間一般の性質から来るもの、個人の経験から来るもの、人と人の言葉のやりとりから来るもの、そして時代が作った理論や権威から来るもの。これが四つのイドラです。
① 種族のイドラ――人間であること自体が生む歪み

最初のイドラは、個人差ではなく、人間という種に共通するクセです。人は世界をそのまま受け取るより、世界に意味を与えたくなります。ばらばらの出来事を、分かりやすい筋書きにまとめ、偶然にも理由を見つけ、少ない材料からでも「きっとこうだ」と言いたくなる。ベーコンは、この「分かりやすさへ吸い寄せられる力」を警戒しました。
このイドラが厄介なのは、頭がよい人ほど精密に働いてしまう点です。仮説を作る力が強いほど、世界がその仮説に沿って見えてしまう。すると観察は、未知を開くためではなく、すでにある筋書きを補強するために働くようになります。だからベーコンは、探究の最初の敵として、外の世界よりも先に、こうした“人間の自然な働き”を置いたのです。
② 洞窟のイドラ――個人の洞窟が作る見え方の偏り
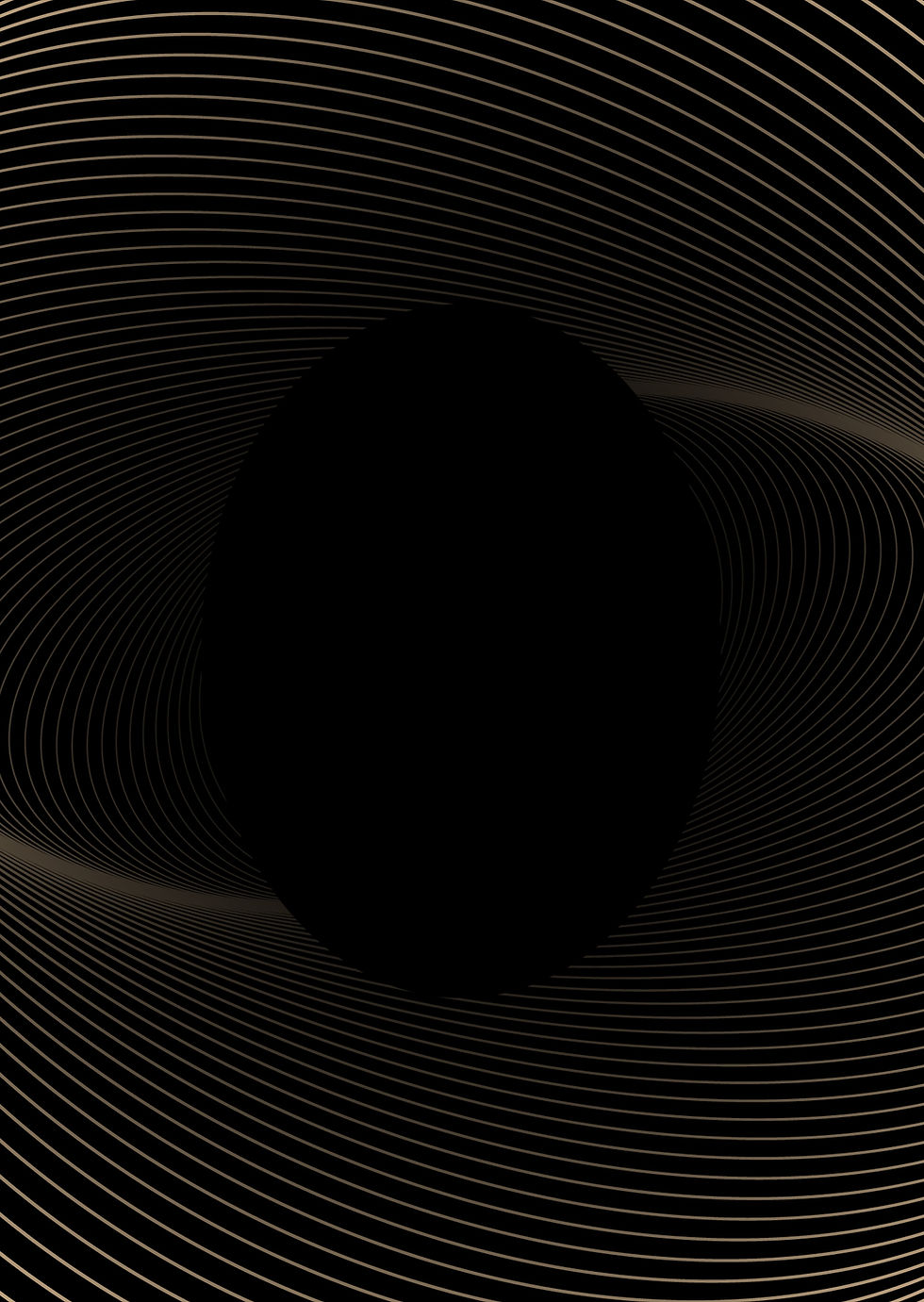
次のイドラは、人間一般ではなく、個人ごとに異なる歪みです。育ち、経験、好み、得意不得意、信念。そうしたものが、それぞれの「洞窟」を作り、同じ事実を見ても、強調される点と見落とされる点を変えてしまう。ベーコンは、ここに「学びの個性」だけで片づけられない危うさを見ました。
個人の洞窟が問題になるのは、洞窟の中が世界の全部になってしまうときです。たとえば、ある経験が強烈であるほど、それが説明の中心になり、別の可能性が薄れていく。ある視点が鋭いほど、その視点以外が“見えないもの”になっていく。洞窟のイドラは、探究が「世界を見る」よりも、「自分の経験を再確認する」方向へ滑るときに顔を出します。ベーコンはそれを、性格の問題ではなく、視野の構造として捉えました。
③ 市場のイドラ――言葉のやりとりが生む歪み

三つ目のイドラは、社会の中で生まれます。人は一人で考えるだけでなく、言葉を通して考えます。言葉があるから共有できるし、議論もできる。しかし、その言葉が雑に使われたり、意味が曖昧なまま流通したりすると、言葉のほうが人を動かしてしまう。ベーコンが「市場」と呼んだのは、まさに言葉が行き交う場です。
ベーコンの視点が鋭いのは、言葉の問題を「表現の問題」としてではなく、「認識の問題」として見ている点です。言葉が曖昧だと、私たちは曖昧なものを理解した気になります。さらに、同じ言葉を使っているから分かり合えていると思い込みます。しかし実際には、同じ言葉にそれぞれ違う像を乗せたまま進んでしまう。その結果、議論は噛み合っているようで噛み合わず、探究は深まっているようで深まらない。市場のイドラは、探究が言葉の勢いに飲まれて、現実から浮いていくときの入り口です。
④ 劇場のイドラ――理論や権威が作る舞台の歪み

最後のイドラは、さらに大きいところから来ます。時代が作った学説、立派に整えられた体系、伝統として受け継がれてきた物語。それらは、舞台装置のように、世界の見え方を最初から決めてしまう。ベーコンはこれを「劇場」と呼びました。劇場では、物語が先にあり、事実はその物語の役者として配置されます。
もちろん理論は必要です。ただ、理論が強すぎると、観察が理論に従属します。すると、事実が新しい問いを生むのではなく、理論を守るための材料になります。ベーコンが批判したのは、「理論があること」ではなく、「理論が先に舞台を作ってしまうこと」です。探究が、現実に触れて更新されるものではなく、最初から完成した物語の確認作業になってしまう。ベーコンはそこにメスを入れたかったのだと思います。
ここまで見てくると、イドラは「人は間違える」という一般論ではなく、かなり実務的な発想だと分かります。思い込みは消せない。ならば、どこから入ってくるのかを分けて、名前をつけて、扱える形にする。人間一般(種族)、個人(洞窟)、言葉の流通(市場)、時代の体系(劇場)。ベーコンは、探究が外の世界に届かない理由を、外の世界の難しさだけでなく、こちら側の仕組みとしても説明しようとしました。
そして、その説明の仕方が、探究にとって大事です。自分を責めずに、誰かを責めずに、でも思い込みを見逃さずに、前に進むための考え方になるからです。
3.探究の現場で起きる「ベーコン案件」3つの場面
ここからは、イドラが抽象的な話ではなく、探究のプロセスの中でどう顔を出すのかを、探究学習の現場に引き寄せて見ていきます。
【場面1】調べる前に、もう答えがある
探究の出発点で「たぶんこうだと思う」が出るのは、むしろ自然です。問題は、その瞬間から、調査が「未知を開く作業」ではなく、「思った通りだと確認する作業」に変わってしまうことです。ベーコンの言葉で言えば、人間は少ない情報でも筋書きを作りたくなる(種族のイドラ)。だから仮説ができた途端に、頭は“証拠を探す目”ではなく、“筋書きを支える材料を拾う目”になりやすいのです。
この歪みを止めるコツは、仮説を消すことではなく、仮説を「一つ」にしないことです。探究の早い段階で、あえて分岐を作ります。
たとえば、最初の「たぶんこうだ」を A案として置いたら、同時に「逆でも説明できる」B案を、わざと作ります。ここでのポイントは、B案が正しいかどうかではなく、「自分の頭が一方向へ吸い寄せられるのを防ぐ壁」を置くことです。
そして調べる時は、「Aを支持する材料」と「Bを支持する材料」を同じだけ集めます。このとき、AとBは立派な理論である必要はなく、「A:こういう理由かもしれない」「B:別の理由かもしれない」程度で十分です。最後に、集まった材料を見ながら「Aが強い/Bが強い/どちらも弱い」を判断します。すると探究が、結論ありきではなく「条件を見つける」方向へ向かいます。
【場面2】インタビューが“欲しい言葉取り”になる
聞き取りをするときに起きやすいのが、相手の現実を持ち帰るのではなく、「自分が期待している言葉」を持ち帰ってしまうことです。これは、個人の関心や経験が見え方を変える(洞窟のイドラ)うえに、言葉が先に立つと現実が現実として見えなくなってしまう(市場のイドラ)という、二つの力が重なって起きます。
たとえば「地域活性」「主体性」「学力」など、便利だけれど曖昧な言葉があると、インタビューは楽になります。相手の話の中からその言葉に当てはまりそうな部分だけを拾って、「ほら、そう言ってた」とまとめられるからです。しかしそれをやると、探究の核であるはずの「具体的に何が起きているのか」が抜け落ちます。
ここを立て直す鍵は、相手の話を「それっぽい言葉」でまとめて終わらせないことです。インタビューで持ち帰りたいのは、「主体性」「地域活性」みたいな抽象語そのものではなく、それが実際に表れていた具体的な出来事です。いつ・どこで・誰が・何をして・どうなったのか。まずはこの“場面の記録”を持ち帰る。そのうえで初めて、「今この人が言う主体性とは何か」を確かめられるようになります。
「◯◯だと思いますか?」ではなく、「いつ/どこで/誰が/何をして/どうなりましたか?」という、出来事の輪郭が残る聞き方に寄せます。さらに、相手が抽象語を使ったら、そこで話を終わらせず、次の一歩だけ踏み込みます。「それは、具体的にはどんな場面のことですか?」「その時、あなたは何をしましたか?」「どのくらいの頻度で起きますか?」こうして“言葉”を“出来事”に戻していくと、インタビューの内容は生きた資料になります。
【場面3】発表が上手すぎて、検討や迷いの痕跡が見えない
発表が上手いこと自体は素晴らしいです。けれど、上手さが「最初から結論が決まっていたように見える上手さ」になったとき、探究としては危うくなります。話が流暢で、スライドが整っていて、途中の迷いが消えている。すると、観察や検討が“物語を成立させるための装飾”になりやすい。これが劇場のイドラです。完成された舞台(物語)が先にあって、事実が役者として配置されてしまう。
発表の「完成度」を下げる必要はありません。代わりに、発表の中に検討の痕跡を必ず残すようにします。
たとえば、発表構成に「途中の失敗」を組み込みます。最初に考えた仮説、途中で出会った反例、迷った分岐、ボツになった解釈。これらを「恥ずかしいもの」ではなく「探究の核心」として扱います。
さらに一歩踏み込むなら、結論の前に「途中で何が変わったか」を言語化させます。「調べる前はこう思っていたが、これに出会ってこう変わった」「この反例が出たので、言い方をこう修正した」こういう変化が見える発表は、聴く側にとっても学びになります。探究が“成果発表”ではなく、“思考の共有”になるからです。
4.探究を立て直すための、蜂の往復
ここまで見てきたように、イドラは「知識が足りない」せいで起きるというより、調べ方が進む途中で、自然に入り込む歪みです。だから大事なのは、イドラを知って終わることではなく、イドラが入り込んだときに、探究を立て直せる手立てを持っているかどうかです。
そこでベーコンは、探究の姿勢を説明する比喩として「蟻・蜘蛛・蜂」を持ち出します。材料を集めるだけの蟻でもなく、自分の頭の中だけで糸を紡ぐ蜘蛛でもない。集めたものを、いったん手元で加工し、もう一度確かめ直す蜂。この往復ができると、探究は「結論の確認作業」に陥りにくくなります。
最後に、探究学習の現場でも運用しやすいように、蜂の往復を小さな「1セット」にして整理します。大げさな方法論ではなく、探究が歪みかけたときに戻ってこられる最低限の手順です。
① 事実を並べる
集めた情報を、まず事実として並べます。ここでは解釈を急がず、「見た/聞いた/数えた/起きた」を中心に書き出します。
② イドラを疑う(入口を確認する)
自分たちは、どんなタイプの歪みが入りやすそうかを考えます。人間一般の“筋書き欲”なのか、個人の経験の洞窟なのか、言葉の市場なのか、理論の劇場なのか。ここで必要なのは反省ではなく、歪んでしまう認知を自覚することです。
③ 逆向きの材料を一つ足す
いまの説明に合わないもの、反例になりそうなものを一つだけ探して追加します。大量に集める必要はありません。たった一つでも、探究は「条件」を見つけ始めます。
④ 言葉を場面に戻す
強い言葉(多様性・主体性・学力など)を、そのまま結論にせず、「どの場面で、どんな行動として現れていたか」に言い換えます。言葉を現実に接地させる作業です。
⑤ 暫定結論にする
最後に、結論を「確定」ではなく「暫定」として置きます。「〜だ」と断言するより、「今のところ〜と言えそう」と書き残す。これで探究は次に続きます。
5.まとめ——入口・説明・そして「思い込みの点検」
ソクラテスを扱った第1回では、探究の入口である「問い」と「言葉」を整えることを扱いました。アリストテレスを扱った第2回では、観察を説明へ組み立てるための骨格を見ました。そこまでできると、一見、探究は完成したようにも見えます。
ただ、実際の探究では、入口と骨格が整っていても、いつの間にか結論が先に決まり、調べるほどに自分の考えが補強されていくことがあります。材料が増えるほど、思い込みが減るとは限りません。むしろ材料が増えるぶん、思い込みは「自分でも気づきにくい形」で育ってしまいます。
ベーコンが示したのは、まさにこの部分です。探究がうまくいかない原因を、誰かの性格や能力のせいにせず、「人間なら誰でも入り込ませてしまう歪み」として扱えるようにしたことです。イドラは、思い込みを消すための魔法ではありませんが、思い込みがどこから入り込んだのかを見つけて、探究を立て直すための手がかりになります。
気合で「偏らないようにする」のではなく、手順として「偏りやすさ」を引き受ける。ベーコンは、そのための最初の道具箱を用意した人だと言えます。
次回は、ここまでの「探究の方法」から少し視点をずらして、「探究する主体」である子どもをどう捉えるか、に踏み込みます。ルソーは、子どもを小さな大人として扱うのではなく、固有の発達段階をもつ存在として捉え直しました。そして、教え込みではなく、経験と環境の側から教育を組み替える発想を強く打ち出します。
ベーコンが「思い込みを点検する道具」を提示してくれたとすれば、ルソーは「育ちが起きる環境をどう設計するか」という別の道具を渡してくれます。方法の話から、子ども観と環境の話へ。ここで探究学習の輪郭が、もう一段はっきりしてくるはずです。
方法の話から、子ども観と環境の話へ。ここで探究学習の輪郭が、もう一段はっきりしてくるはずです。




コメント